もったいない!! ~食品ロスをなくそう~
食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。日本では令和5年度に約464万トンの食品ロスが発生したと推計されています。
そのうち、約半分が家庭(約233万トン)から発生しています。(残りは事業者から)
令和元年10月1日に施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」には、国や地方公共団体、事業者の責務だけではなく、消費者の役割として「食品ロスの削減の重要性についての理解と関心を深めるとともに、食品の購入または調理の方法を改善すること等により、食品ロスの削減について自主的に取り組むよう努める。」ことが求められています。
(食品ロスの例)
・食べ切れずに廃棄される。(食べ残し)
・賞味期限切れ等により使用・提供されず、手つかずのまま廃棄される。(直接廃棄)
・厚くむき過ぎた野菜の皮など、不可食部分を除去する際に過剰に除去された可食部分(過剰除去)


食品ロスを減らしましょう(消費者庁) (PDFファイル: 1.3MB)
ファミマフードドライブ(食品ロスの削減と子どもたちの支援)について
家庭での取り組み
食品ロスを減らすために、次のことに気を付けましょう!
【買い過ぎない】
食材を買い過ぎたり、同じ食材を買ってしまったりすると、食材を使い切らずに廃棄してしまうことにつながります。
(取り組み例)
・買い物前に家にある食料品を確認する。
・買い物のリストを作成する。
・使い切れる量を購入する。
【保管方法を確認する】
保管方法を間違えると消費期限を待たずに廃棄することにつながります。
(取り組み例)
・食品ごとの保管方法を確認する。
・冷蔵庫の中を常に整理し、食品の種類や量を確認しやすくする。
・消費期限を確認しておく。
【作り過ぎない】
食事を作り過ぎると廃棄することにつながります。
(取り組み例)
・食べきれる量を把握し、作り過ぎない。
・使い切れなかった食材も適切に保管し、使い切る。
・残った料理もリメイクレシピも活用し、食べ切る。
食品ロス削減レシピ
消費者庁では、食品ロスの削減に向けた様々な取組を行っています。消費者庁のキッチンでは、消費者の皆様が食品ロスを削減する際に参考となるレシピを紹介しています。
生ごみの処理について(水切りをしましょう)
生ごみは、燃やせるごみの約35%を占めています。そのうち約80パーセントが水分です。
生ごみの水分をひと絞りするだけでごみが減量できるだけでなく、においや虫の発生も抑制できます。
- この記事に関するお問い合わせ先














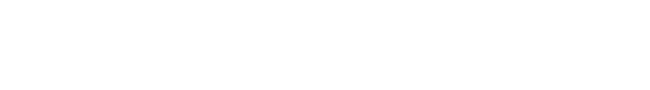
更新日:2024年10月01日