介護保険制度について
介護保険は、高齢者の介護を国民全体で支え合う制度です。ここでは介護保険の仕組みについて説明します。
介護保険とは:介護保険制度、介護保険の加入者などについて説明します。
介護サービスを利用するには:要介護認定の申請などについて説明します。
保険料について:介護保険の保険料について説明します。
サービス利用の自己負担と軽減制度:介護保険で受けられるサービスを利用するときの自己負担(利用者負担)について説明します。
介護保険とは
介護保険のしくみ
高齢化の進行に伴い、寝たきりや認知症があるなど、介護を必要とする高齢者が急速に増加していくとともに、核家族化や介護している家族の高年齢化、高齢者夫婦のみの世帯の増加など、要介護高齢者を支えてきた家族をとりまく状況も大きく変化してきました。
こうした状況をふまえ、できる限り、自宅で自立した日常生活を送ることができるように支援し、今まで家族が抱えてきた介護の負担を社会全体で支え合うために介護保険制度が始まりました。
介護保険制度は、相互扶助の考えにたって全員が保険料を負担し、誰もが介護が必要になったときに、認定を受け、サービスを利用するしくみになっています。
介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。
40歳以上の方は、原則として介護保険の被保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割、2割または3割を負担することでサービスを利用することができます。
介護保険の対象となる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、認定を受け、サービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態になった場合に、認定を受けて、サービスが利用できます。
特定疾病とは
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊柱管狭窄症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 脳血管疾患
- 多系統萎縮症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 脊髄小脳変性症
- 慢性閉塞性肺疾患
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用したいときは、まずは要介護認定を受ける必要があります。
認定結果により、要介護1~5の方は「介護サービス」を、要支援1・2の方は、「介護予防サービス」がご利用できます。
在宅サービスを利用するためには、ご本人の心身の状況にあわせ、どのようなサービスをどれくらい利用するかというケアプラン(介護サービス計画・介護予防サービス計画)が必要です。
要介護認定・要支援認定区分変更申請について
要介護(要支援)認定を受けている方が、認定有効期間内に心身の状態の変化により、介護の必要な程度に変化がある場合に、要介護(要支援)状態区分の変更が必要であるとして行う申請です。
要介護認定・要支援認定区分変更申請の必要な方は高齢介護課介護保険班にお問い合わせください。
要介護1~5の方は
居宅介護支援事業者などに依頼して利用するサービスを盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
海南市内の居宅介護支援事業所一覧 (PDFファイル: 104.8KB)
居宅サービス計画作成依頼届出書 (PDFファイル: 103.0KB)
居宅サービス計画作成依頼届出書 (Excelファイル: 20.2KB)
介護保険要介護・要支援認定申請書 (Excelファイル: 65.5KB)
要支援1・2の方は
介護保険の介護予防サービスを利用します。海南市地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。
また、地域包括支援センターは高齢者の方やご家族、地域の方々からの高齢者の方の相談・悩みをお聞きして適切なサービスや機関につなげていくために設置されています。お気軽にご相談ください。
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(PDFファイル:95.3KB)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(Wordファイル:49.5KB)
海南市地域包括支援センター
所在地:海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8762
保険料について
サービス利用の自己負担と軽減制度
自己負担(利用者負担)
介護保険のサービスを利用した場合、利用者は、かかった費用の1割、2割または3割を負担します。ただし、高額介護サービス費の支給による負担上限があります。
| 利用者負担割合 | 条件 |
|---|---|
|
3割
|
以下の条件をすべて満たす人
|
| 2割 |
利用者負担割合3割の条件に当てはまらない人で、以下の条件をすべて満たす人
|
| 1割 |
利用者負担割合2割・3割の条件に当てはまらない人 |
注意1:合計所得金額とは、給与収入・年金収入・事業収入などから給与所得控除・年金所得控除・必要経費などを控除した額のことです。平成30年8月以降は、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」を用います。
注意2:その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を引いた金額です。
利用者負担の軽減
サービスを利用した費用が高額になったときや、収入が少ない人のために様々な支援対策が行われています。
〔1〕食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度
施設サービス・短期入所(ショートステイ)を利用した場合に、別途、食費・居住費(滞在費)が必要となりますが、所得の低い方等には食費・居住費(滞在費)が軽減される場合があります。
| 段階区分 | 対象者 |
|---|---|
| 第1段階 |
|
| 第2段階 |
|
| 第3段階1 |
|
| 第3段階2 |
|
【対象者について】
1.配偶者が別世帯(住民票上)である場合は、その配偶者も市町村民税非課税であることが適用条件となります。
2.預貯金等について、配偶者がいる場合には、同居・別居に関わらず夫婦の合計額で判定します。なお、ローン等の借入れ(負債)については証明できるものを添付することで、資産の合計から差し引いて判定します。
※令和7年8月から、80.9万円に変わります。
| 利用者負担段階 | 食費の負担限度額 | 居住費(滞在費)の負担限度額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段階区分 | 施設サービス | 短期入所サービス | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | |
| 第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | |
| 第3段階1 | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | |
| 第3段階2 | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) |
430円 | |
注釈:介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。
軽減制度を利用するための手続き
- 事前に申請が必要となります。
軽減制度を利用するためには、高齢介護課に「介護保険負担限度額認定申請書(裏面が同意書になっています)」に「預貯金額等がわかるものの写し」を添付して提出してください。 - 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)となります。
- 郵送での申請も可能です。ただし、受付日は申請書の受理日となります。
- 軽減制度の対象となる方には高齢介護課から「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、サービス事業者に提示してください。
- 有効期間は申請日の属する月の初日から翌年の7月末日までとなります。(ただし1月から7月の間に申請をされた場合はその年の7月末日までです)
- なお、段階区分の見直しは毎年8月に行なわれますので、新たに申請が必要です。
令和6年度注意事項(令和6年8月1日〜令和7年7月31日)
介護保険負担限度額認定申請についての注意事項(PDFファイル:104.2KB)
令和7年度注意事項(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)
介護保険負担限度額認定申請についての注意事項(PDFファイル:94.7KB)
提出していただく書類(記入漏れ、添付漏れがある場合は、本市から返送し、再度提出していだくことになり、認定が遅れる場合もありますので、十分確認してください。)
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書(申請書の裏面)
3.預貯金額等がわかるものの写し(通帳のコピー等)※生活保護受給者は添付不要
令和6年度(令和6年8月1日〜令和7年7月31日)申請用様式
令和6年度介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(PDFファイル:215KB)
令和6年度介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(記入例)(PDFファイル:191.6KB)
令和7年度(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)申請用様式
令和7年度介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(PDFファイル:214.9KB)
令和7年度介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(記入例)(PDFファイル:188.6KB)
介護保険負担限度額認定申請書と介護保険負担限度額認定同意書は両面印刷してください。両面印刷ができない場合は、ホッチキス止めをして提出してください。
〔2〕社会福祉法人等による生活困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が県及び市町村に利用者負担軽減制度の実施を申し出ているサービスについて、利用者負担を軽減する制度です。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
本制度の実施事業所一覧については以下をご参照ください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業について(和歌山県HP)
軽減の対象となる費用
- 介護保険サービスの利用者負担額
- 食費、居住費(滞在費)及び宿泊費
軽減額
利用者負担額の1/4を軽減
(老齢福祉年金受給者は1/2、生活保護受給者は個室居住費の全額)
対象者
対象となる方は市町村民税非課税者であって、以下のすべての対象要件を満たしたうえで、利用料の減額を行わなければ生活が困難であると認められる場合の方が対象となります。
1.年間収入※1が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
2.預貯金等(有価証券を含む)の合計が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円加算した額以下であること。
3.世帯全員について、自分が住んでいる住居・土地以外に活用できる資産を所有していないこと。
4.負担能力のある親族等に扶養※2されていないこと。
5.介護保険料を滞納していないこと。
※1収入には、障害年金・遺族年金等の非課税収入も含めます。
※2親族等の所得税・市町村民税の扶養控除において、扶養親族となっている場合や、社会保険・健康保険組合・共済保険の医療保険に加入している場合は、親族等からの扶養を受けていると考えられるため、要件を満たさないこととなります。
提出していただく書類
1.社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書
2.収入等申告書
3.預貯金額等がわかるものの写し(通帳のコピー等)
4.加入している医療保険証の写し
※生活保護受給者は申請書(上記1)および生活保護受給証明書をご提出ください。(上記2.3.4は提出不要)
令和6年度(令和6年8月1日〜令和7年7月31日)申請様式
令和6年度社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(PDFファイル:90.2KB)
令和6年度社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(記入例)(PDFファイル:73.8KB)
令和7年度(令和7年8月1日〜令和8年7月31日)申請様式
令和7年度社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(PDFファイル:90.2KB)
〔3〕高額介護(予防)サービス費の支給について
世帯ごとの介護サービスの利用料の1ヶ月の合計額※が、下表の上限額を超えた場合、その超えた分について「高額介護(予防)サービス費」として支給します。
※高額介護(予防)サービス費の支給対象となる自己負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費、区分支給限度額を超えて利用した分、食費・居住費(滞在費)・日常生活費は含みません。
支給対象となった方には、支給申請書を郵送させていただきますので、必要事項を記入等の上、海南市高齢介護課に提出してください。一度申請されると、以降は自動的に支給されます。
| 利用者負担段階区分 | 上限額(月額) |
| 市町村民税課税世帯で、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 市町村民税課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税世帯で、課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
|
世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円※以下 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円(世帯) |
※令和7年8月から、80.9万円に変わります。
障害者控除
「障害者控除対象者認定書」の発行について
障害者手帳等の交付を受けていない方でも、下記の対象者は申請により「障害者控除対象者認定書」が発行され、税法上の障害者控除を受けることができます。
※障害者控除とは、納税者本人または扶養者が障害者である場合、一定の金額の所得控除を受けることが出来る制度です。
【対象者】
65歳以上の方で、障害者控除の対象となる年の12月31日時点において要介護認定資料もしくは訪問調査結果の「日常生活自立度」が下表の基準に該当する方
| 認定結果 | 障害の程度 | 基 準 |
|---|---|---|
| 障害者 | 知的障害者(軽度)に準ずる者 | 認知症II |
| 知的障害者(中度)に準ずる者 | 認知症III | |
| 身体障害者(3級~6級)に準ずる者 | 障害A1又はA2 | |
| 特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 認知IV又はM |
| 身体障害者(1級~2級)に準ずる者 | 障害B1以上 |
【申請に必要なもの】
申請者および対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
【申請場所】
高齢介護課、下津行政局、各支所・出張所
障害者控除対象者認定申請書 (Excelファイル: 20.1KB)
障害者控除対象者認定申請書 (PDFファイル: 119.7KB)
ダウンロード
海南市内の居宅介護支援事業所一覧 (PDFファイル: 104.8KB)
居宅サービス計画作成依頼届出書 (PDFファイル: 103.0KB)
居宅サービス計画作成依頼届出書 (Excelファイル: 20.2KB)
介護保険 要介護・要支援 認定申請書【申請にあたってのお願い】 (PDFファイル: 345.5KB)
介護保険 要介護・要支援 認定申請書【申請にあたってのお願い】 (Excelファイル: 65.5KB)
要介護・要支援認定申請取下書 (PDFファイル: 97.4KB)
介護保険被保険者証等再交付申請書 (PDFファイル: 81.4KB)
※ 介護保険被保険者証、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)、介護保険受給資格証明書、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証の再交付に利用できます。
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 95.3KB)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 (Wordファイル: 49.5KB)
要介護認定等の資料提供に係る申出書(本人同意書) (PDFファイル: 107.8KB)
※ 要介護認定等の資料提供に係る申出書(本人同意書)は両面印刷してください。
※ 要介護認定等資料の郵送を希望される場合は返信用封筒をご用意ください。
介護保険ガイドブック
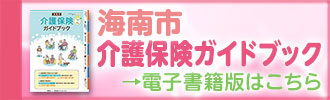
介護保険に関する最新情報はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp














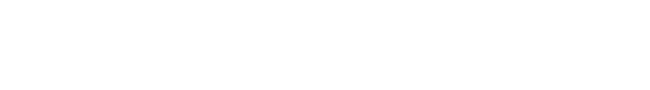
更新日:2025年04月15日