重度心身障害児者医療費助成制度
対象
満65歳に達する日以前に下記のいずれかの障害に該当される人
- 身体障害者手帳1級、2級、3級の交付を受けている人
- 療育手帳A1、A2の交付を受けている人
- 特別児童扶養手当1級を受給されている人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- その他市長がこれらと同等程度の身体又は精神の障害を有すると認めた人
条件
次の1から3のすべてに該当する人
- 海南市に住所を有し、健康保険に加入されている人
- 生活保護法その他法令により医療費の全額を公費で負担されていない人
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以下である人
内容
保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。
ただし、入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種、健康診断、文書料等は助成の対象外です。
また、加入している健康保険から高額療養費や附加給付等が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
注意:その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
助成の受け方
和歌山県内の医療機関で受診するとき
医療機関の窓口で健康保険証と海南市が発行する受給資格証を提示してください。
自己負担分は、医療機関から海南市へ請求がありますので医療機関の窓口で支払う必要はありません。(保険診療分以外のものは助成の対象となりません。)
和歌山県外の医療機関で受診するとき
自己負担分を医療機関の窓口で支払い、受診月の翌月以降に下記のものを持って市役所社会福祉課、下津行政局または各支所出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 受給資格証
- 振込先がわかるもの(預金通帳等)
- 領収書(医療機関名、領収印、診療日、対象者の氏名、保険点数、自己負担額の記載があるもの)
入院等で医療費が高額になることが見込まれる場合は、加入している健康保険で「限度額適用認定証」の交付申請の手続きをお願いします。
入院などで医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証等を提示すれば、1か月の医療機関等の窓口での支払いを一定金額に留めることができます。
ただし、差額ベッド代など保険診療対象外は除きます。加入している保険者に事前に限度額適用認定証等の申請手続きをお願いします。
学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、重度心身障害児者医療費助成制度の助成対象となりません。
保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校等の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられます。詳しくは学校等にお問い合わせください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合は、重度心身障害児者医療費助成制度の助成対象となりません。学校等でけがをしたときは、「重度心身障害児者医療費受給資格証」を使用しないでください。
交通事故等(第三者行為)に遭った場合
交通事故などに遭ったときは、市役所に届出が必要な場合があります。交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合の治療費は、本来その第三者が負担するべきものです。重度心身障害児者医療費助成の対象者である方が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷または病気になり、かつ、健康保険及び重度心身障害児者医療費受給資格証を使用する場合は、ご加入の健康保険への届出とともに市役所(国保の方は保険年金課、国保以外の方は社会福祉課)への届出も必要です。
ジェネリック医薬品使用にご協力ください
ジェネリック医薬品は、効き目や安全性が先発医薬品と同等であると国から承認された安価な医薬品です。医療費軽減につながり、医療費助成制度を将来にわたり持続可能なものにするため、皆様のご協力をお願いいたします。
適正受診にご協力ください
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。
必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様に御負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。
- 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
- 夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談の利用を考えましょう。
- 普段の健康状態や服薬歴を把握してくれる「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局(薬剤師)」を持ち、気になることがあれば相談しましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp














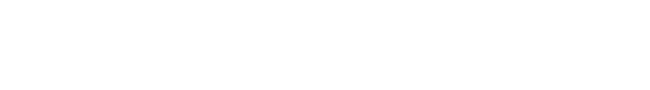
更新日:2021年03月01日