高額療養費と限度額適用認定証
高額療養費制度について
医療機関等に支払った1か月(月の1日から月末まで)の医療費の自己負担について、申請により認められると、自己負担限度額を超える額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は世帯の所得等の状況や、年齢等により定められています。(8月~12月診療については前年中、1月~7月診療については前々年中の所得状況によります)
年齢や所得による自己負担限度額(月額)について
|
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 注1 |
|---|---|---|
|
【区分ア】 被保険者ごとの所得 注2 の合計が901万円を超える世帯 |
252,600円+ |
140,100円 |
|
【区分イ】 被保険者ごとの所得 注2 の |
167,400円+ |
93,000円 |
|
【区分ウ】 被保険者ごとの所得 注2 の |
80,100円+ |
44,400円 |
|
【区分エ】 被保険者ごとの所得 注2 の |
57,600円 |
44,400円 |
|
【区分オ】 住民税非課税世帯 注3 |
35,400円 |
24,600円 |
|
所得区分
|
外来 |
外来+入院 |
|---|---|---|
|
【現役並み3】 (同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の70~74歳の被保険者がいる方) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
|
|
【現役並み2】 (同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70~74歳の被保険者がいる方 (注4) ) |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
|
|
【現役並み1】 (同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70~74歳の被保険者がいる方 (注4) ) |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
|
| 【一般】 |
18,000円 ただし、年間144,000円まで 注6 |
57,600円 ただし、4回目以降 注1 は44,400円 |
| 低所得者2【区分2】 | 8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者1【区分1】 | 8,000円 |
15,000円 |
※月の途中で75歳の誕生日を迎えた方については、その月の自己負担限度額が2分の1になります。
注1 診療月以前の12か月以内に世帯で高額療養費の支給を受けた(自己負担限度額まで達した)月が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担額(「多数回該当」といいます)。
注2 ここでの「所得」とは、総所得金額等から43万円を差し引いたもの(マイナスになった場合は0とする。)を言います。
注3 ここでの「住民税非課税世帯」とは、世帯主及びすべての被保険者が住民税非課税または免除の世帯を言います。
注4 ただし、特例規定により、一般となる場合があります。詳しくは、保険年金課までお問合せください。(電話番号:073-483-8404)
注5 ここでの「所得が一定基準に満たない世帯」とは、世帯主及びすべての被保険者に所得(ただし、公的年金等については控除額を80万円として所得を算定します。)がない世帯を言います。
注6 8月診療から翌年7月診療までの、年間の自己負担限度額。
高額療養費の計算方法
月の1日から月末まで、歴月ごとの診療について計算します。
室料差額などの保険適用外の負担や入院時の食事代は計算の対象外です。
| 70歳未満の方の場合 |
被保険者ごと、医療機関ごと(同じ医療機関であっても入院と外来、医科と歯科は別。ただし、院外処方による調剤は処方せんを出した医療機関と同一とみなす)に自己負担を分けて、21,000円以上となる自己負担のみ合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。 |
| 70歳以上の方の場合 |
医療機関等ごとに自己負担を分ける必要はありません。外来の場合は被保険者ごとに自己負担(金額は問いません)を合算し、その合算額が外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。また、入院があった場合は70~74歳のすべての被保険者の外来と入院の自己負担(金額は問いません)を合算し、その合算額が外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。 |
|
70歳未満の方と70歳以上の方との合算の場合 |
まず、70歳以上の方の高額療養費を算定します。それを支給し、なお残る70歳以上の方の自己負担と70歳未満の方の合算できる21,000円以上の自己負担とを合算し、その合算額が70歳未満の方の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。 |
限度額適用認定証について
70歳未満の方及び70歳以上で低所得者1・2又は現役並み1・2に該当する方は、申請により限度額適用認定証等の交付を受けて医療機関等に提示すれば、医療機関等に支払う自己負担が医療機関等ごとに自己負担限度額までとなります。
※医療機関などでオンライン資格確認ができる場合、限度額適用認定証の提示は不要です。詳しくは受診される医療機関などにお問い合わせください。
※70歳以上で現役並み所得者3及び一般の方は、被保険者証(保険証)と高齢受給者証を医療機関等で提示するのみで自己負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証等は必要ありません。
※住民税非課税世帯は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」となり、入院時の食事代なども減額されます
申請に必要なもの
- 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください )
- 資格確認書または被保険者証(保険証)
- 世帯主の個人番号カードまたは通知カード
- 受診者の個人番号カードまたは通知カード
マイナ保険証をぜひご利用ください
「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
◆ご利用にあたっての注意事項◆
- 「マイナ受付」が導入されていない医療機関等では利用できません。
- 直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらにうける場合は、別途申請手続きが必要です。
- 世帯に所得未申告の方がいた場合、正確な所得区分の判定ができない場合があります。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で適用区分が確認できません。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
医療費の自己負担が自己負担限度額以上になった場合は、高額療養費支給申請を行ってください!
高額療養費の支給対象がある場合、その支給を受けるには申請が必要です。該当する世帯には、お知らせを送付しています。
国保加入の世帯員が70歳以上の方のみで構成される場合、申請手続きを簡素化しています。対象の世帯には簡素化対象用の支給申請書を送付しお知らせしています。
また、制度上、振込までには数か月以上かかる場合もありますので、ご了承ください。
申請に必要なもの
- 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください )
- マイナ保険証、資格確認書または被保険者証(保険証)
- 世帯主の個人番号カードまたは通知カード
- 受診者の個人番号カードまたは通知カード
- 医療費の領収書
- 国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)
※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。
※マイナ保険証とは、保険証として登録したマイナンバーカードを言います。
申請窓口
保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp














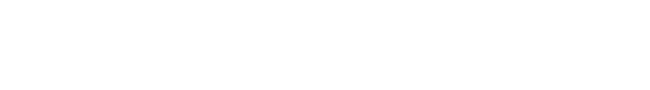
更新日:2024年12月02日