認可外保育施設に係る第2子以降保育料助成について
令和元年10月からの国による幼児教育・保育無償化施策の一環として、0歳児から2歳児に係る認可外保育施設等の保育料については、保護者が認可保育所と同等の「保育の必要性」の認定を受けた場合、非課税世帯に限り一定額を限度として無償としているところですが、令和3年度から第2子以降を養育する世帯にまで対象を拡充しております。
上記の制度の適用を受けようとする場合のお手続きは、次のとおりです。
対象者
次の1から3の条件のいずれにも当てはまる子どもの保護者は、認可外保育施設に係る保育料の助成を受けることができます。
- 認可保育施設と同等の保育の必要性の認定「教育・保育給付認定」を受けていること
- 利用する子どもが、0歳児から2歳児まで(当該年度の4月2日時点の満年齢)でかつ第3子以降または低所得者世帯(非課税世帯を除く)の第2子であること
- 保育所・認定こども園・地域型保育事業を併用していないこと
注意:非課税世帯は国による無償化制度「子どものための施設等利用給付」の対象となります(内部リンク「子育てのための施設等利用給付認定申請について」参照)。
申請手続及び受付期間
上記の制度の適用を受けるためには、事前に認可保育施設と同等の保育の必要性の認定「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。申請書類は、受付期間内に必ず海南市役所子育て推進課へ提出してください。
受付期間:利用開始希望月の前月の15日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
給付内容
認定を受けた子どもの保護者が、有効期間内において、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払った場合に、月額42,000円を上限として利用料相当額を給付します。
認定の要件
保育の必要性(子どもが家庭で保育を受けることができないとする事由)
保育の必要性が認められるのは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、家庭において子どもを保育することが困難な場合です。
- 1か月に48時間以上労働することを常態としている場合
- 妊娠中であるか又は出産後間がない場合
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
- 就学している場合
- その他、保育が必要な状態にあると海南市長が認める場合
非課税世帯・低所得者世帯
非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母の市町村民税がいずれも非課税(市町村民税が全額免除となった場合、未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなした場合に非課税となる場合を含む。)である場合をいいます。
また、低所得者世帯とは、子どもと同一世帯の父母の市町村民税所得割の合計額が57,700円未満である場合をいいます。
注意1:上記に該当する場合であっても、父母の年収の合計が130万円未満で、同居またはその父母を扶養する祖父母に市町村民税が課税される場合は、市町村民税非課税世帯には該当しないものとします。
注意2:保護者が里親である場合または保護者が生活保護法第6条に規定する被保護者である場合、市町村民税の課税状況にかかわらず、非課税世帯として取り扱います。
市町村民税所得割の合計額の確認方法(給与等からの天引きの場合) (PDFファイル: 218.2KB)
市町村民税所得割の合計額の確認方法(納付書・口座振替払いの場合) (PDFファイル: 207.9KB)
認定申請に必要な書類
「教育・保育給付認定申請書」のほか保育の必要性の認定要件に応じ必要書類を提出してください。申込児童1人につき、1部が必要となります。
これらの書類は、保育の必要性を確認するための重要な資料です。書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認ください。
教育・保育給付認定申請書 (PDFファイル: 131.8KB)
教育・保育給付認定申請書(記入例) (PDFファイル: 145.4KB)
保育の必要性の認定要件等 (PDFファイル: 103.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp














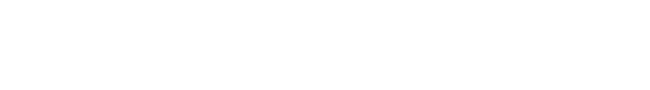
更新日:2024年08月23日